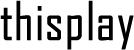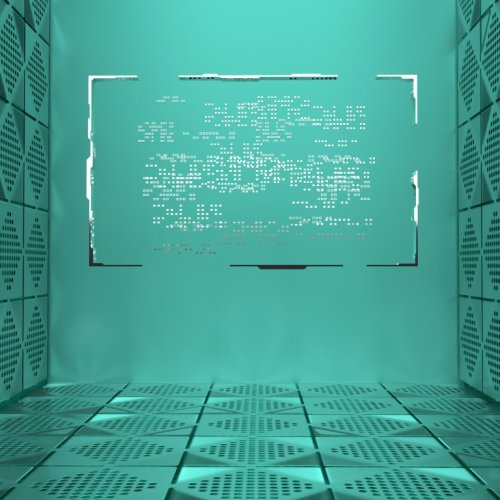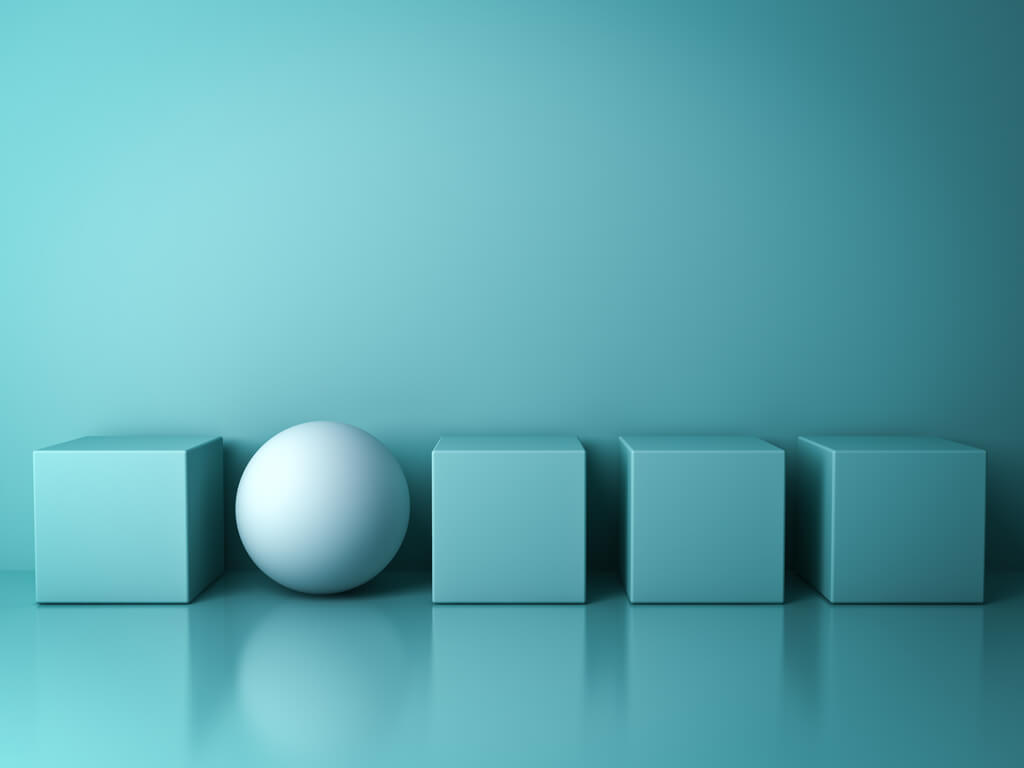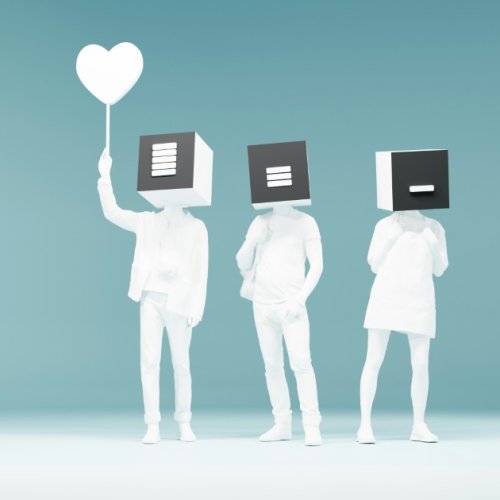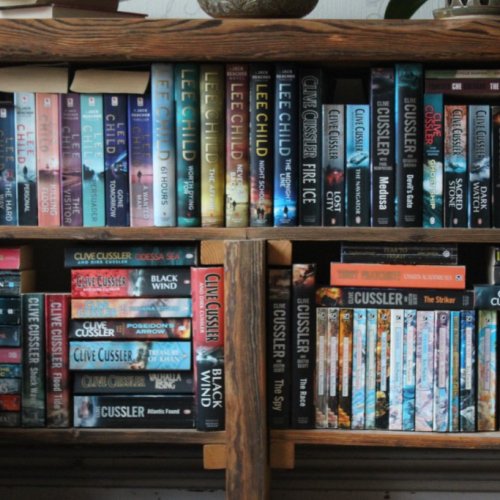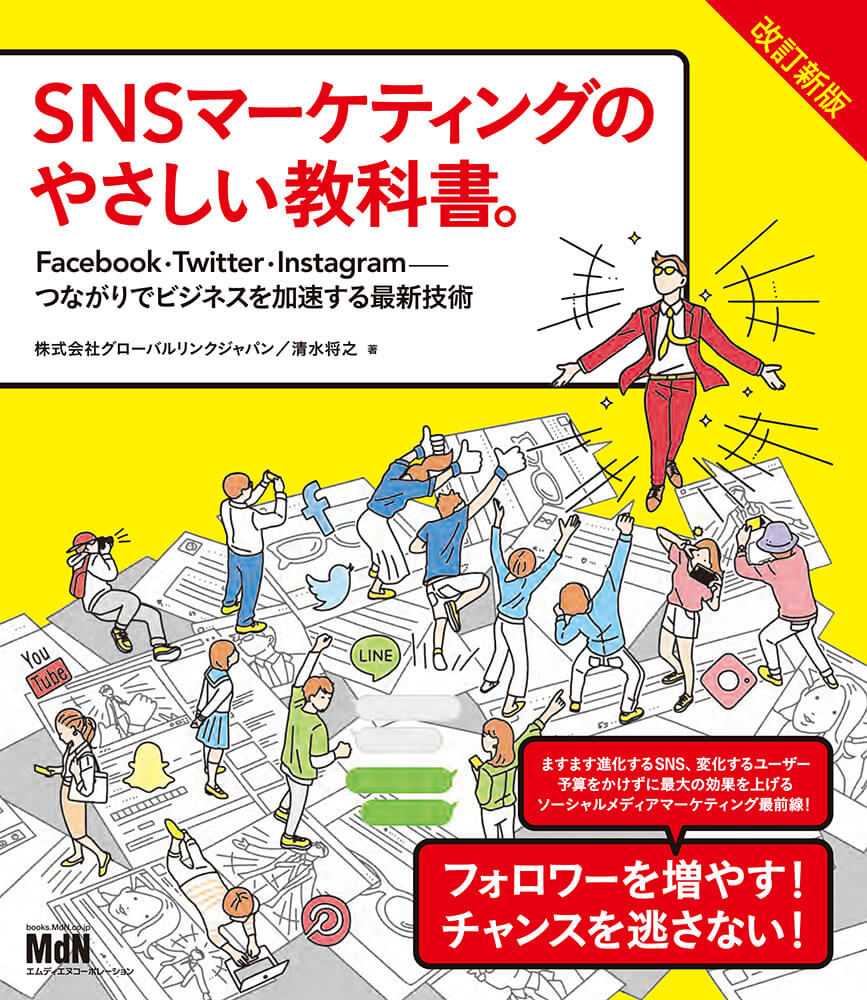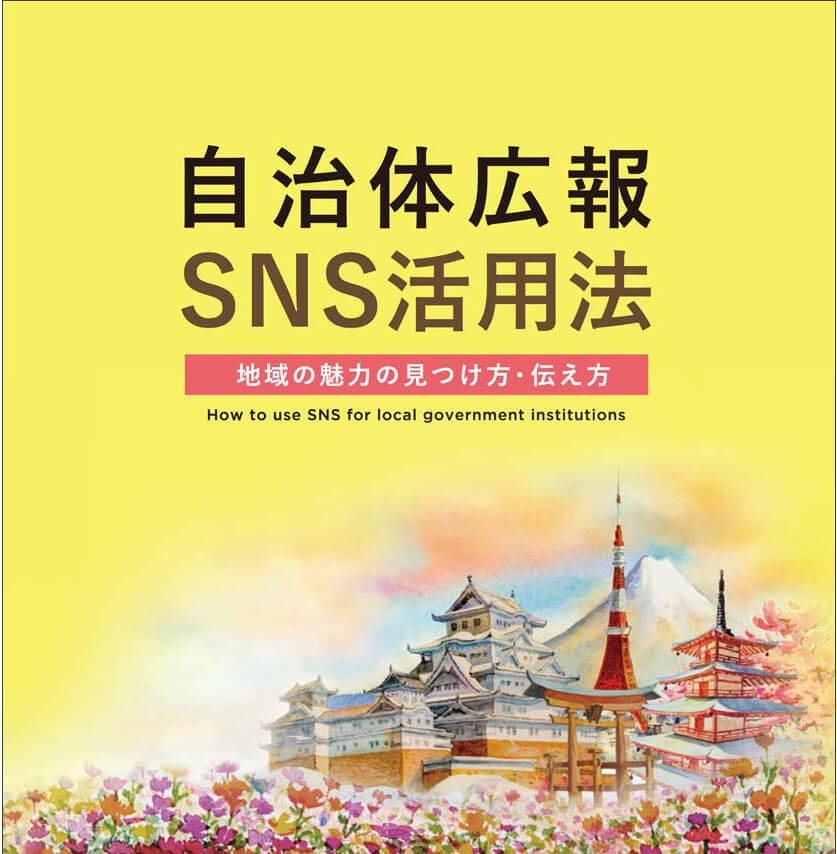公営競技のSNSは「結果速報型」から「ストーリー型」へ──ファン行動の変化と運用設計の最適解
公営競技のSNS運用は、結果速報を中心とした「情報提供型」から、ファンが選手や競技に感情移入し、応援意識を育てる「ストーリー型」へシフトしています。近年は、SNSの投稿内容が観戦・来場・視聴の意思決定に影響を与える場面が増えています。各競技がファン層の若返り・定着・離脱防止に課題を抱える中で、SNSをどのように位置づけるかが重要なテーマになっています。本記事では、ファン行動の変化と、SNS運用の最適な設計を解説します。
結果速報だけでは届かなくなった理由
結論として、結果発表だけではファンの感情が動きにくくなっています。SNS上に娯楽が溢れている現在、ファンは「勝った・負けたの情報」よりも、「努力・葛藤・背景」への共感を価値に感じています。
その背景には、視聴行動の変化があります。Z世代を中心に、スポーツ・eスポーツ・アイドルなどの分野で「推し文化」が広がり、選手の魅力を深く知った上で競技を楽しむスタイルが増えています。公営競技でも同様で、例えば「新人のB選手がどんな思いでレースに挑んでいるのか」「ベテランのA選手が復帰までどんな治療とトレーニングをしていたのか」などの情報に触れることで、自然と応援したくなる心理が生まれます。
SNSの目的は投票行動を直接促すことではなく、競技・選手・チーム・会場・スタッフへの興味と愛着を育てることです。ストーリー型の発信は、ファンにとって「参加している実感」を生む接点になります。
非開催日のコミュニケーションがファンの熱量を決める
開催日だけの投稿では、ファンとのつながりが途切れやすくなります。むしろ大切なのは非開催日のコンテンツ設計です。
投稿例としては、
・選手のルーティーン・こだわり・用具への想い
・印象に残っているレースの振り返り
・ファンの質問に答えるコーナー
・会場の歴史や豆知識
などが効果的です。
これらは結果とは直接関係がなくても、競技や選手の魅力や努力が伝わるため、ファンの「応援したい気持ち」が育ちます。また、射幸心を煽る表現に依存しないため、公営競技の公共性や公益性を保ちながら発信できる点でも安全です。
このようなストーリー型の投稿を積み重ねたうえで、開催日前後に速報投稿を行うと、リーチ・反応率・視聴率が高まり、ファンの参加意欲も自然と高まります。
運用効果を最大化するKPI設計
SNSの成果を測定する際、投票や払戻を直接のKPIにするのではなく、ファン行動の段階に沿って指標を分けることが重要です。
関心フェーズ:コメント数・保存数・視聴維持率
共感フェーズ:選手名検索の増加・UGC投稿・応援コメント
行動フェーズ:開催情報ページのクリック・公式LINE/アプリ登録
SNSは短期利益ではなく「ファンの熱量を育てる装置」です。これを前提にKPIを設計することで、内部説明や予算獲得がしやすくなり、運用者の心理的負担も軽減されます。
まとめ
・公営競技のSNSは「速報中心」から「ストーリー中心」へ移行しています
・非開催日を含めた365日型コミュニケーションが愛着形成の軸になります
・KPIは投票や払戻ではなく、ファン行動のプロセスに沿って設計することが安全かつ効果的です
SNSは、競技・選手・会場・支える人々への理解と魅力を伝える重要なタッチポイントです。SNSの役割が変われば、ファンの関係性も変わります。